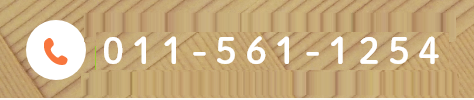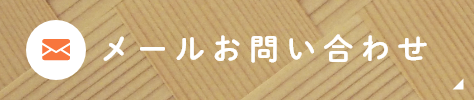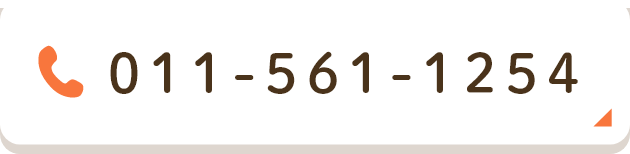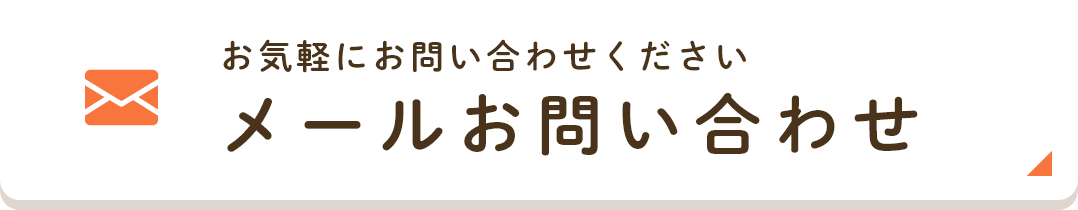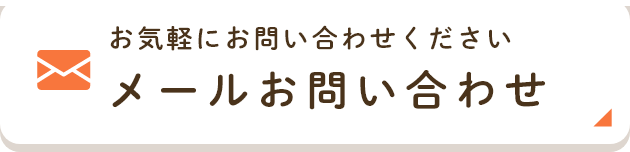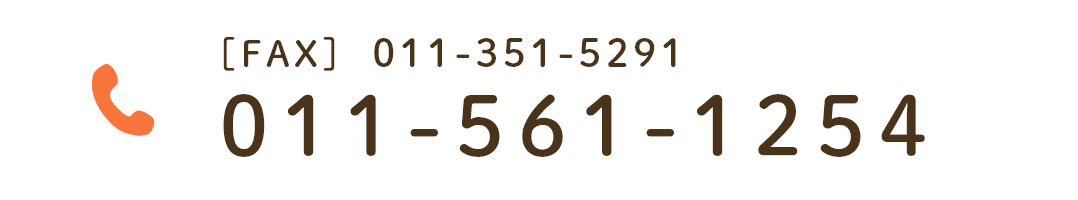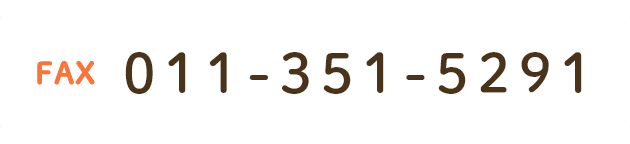こんな症状はありませんか?
以下のような症状のある方は、摂食嚥下障害の可能性が大きく、早めの受診、治療をおすすめします。
- 食事中にむせる
- 噛みにくい、飲み込みにくい
- 飲み込んだあと、のどに何か残っている感じがする
- 食べられるものが少なくなった
- 食事時間が長くなった
- 最後まで食べきれない
- 食後に食べかすが口に残る
- 口が渇く
- 滑舌が悪いと感じる、舌が回らない
- 入れ歯が合わないけど、通院できない
- 歯が痛い、むし歯がある
- 食べものがはさまる
- 要介護の方で、医院に連れて行くのがたいへん
- 要介護の方で、歯みがきができない など
摂食嚥下障害とは

食べものを口まで運び、口に入れ、咀嚼し、飲み込み、胃まで送り込む一連の食事行動。この働きのことを「摂食嚥下」といいます。私たちが、普段、何気なく行っている行為ですが、高齢者になって口、舌、のどなど食べることにまつわる器官の機能が衰えてくると、この行動にもいろいろ問題が起きてきます。それが摂食嚥下障害です。
たとえば、舌の力が弱くなり、その動きが鈍ることで食べものが口に残ったり、飲み込む力の衰えにより、食べものがのどに残ったりします。また、食べたものが飲み込みにくくなり、気管に入ってむせてしまうといったことも、嚥下機能の低下のひとつです。こうしたことから食事が取りづらくなり、栄養が偏ったり脱水を起こしたりしてきます。すると、誤嚥性肺炎が起きるばかりでなく、食べものがのどに詰まって窒息する危険性も…!
そして、誤嚥とは、食べたものがスムーズにのどから食道に入らず、誤って器官に入ってしまうことです。その誤嚥が原因で、窒息や「誤嚥性肺炎」を引き起こす可能性があり、特に高齢者に重症化することもあるので注意が必要です。
摂食嚥下機能の検査
摂食嚥下障害の診断には、診察、検査が必要です。当院では、以下のような検査を行っています。
嚥下機能評価(器機による検査以外)スクリーニング検査
嚥下内視鏡検査

- ベッドサイドでも検査可能。いつも食べているもの、いつもの環境(自宅など)でも検査、評価可能です。
- 検査は、鼻からファイバースコープを挿入した状態で、実際に食べものを食べていただき、その時の咽頭(のどの奥)の状態を見て、評価します。
- 鼻からの検査なので、くしゃみ、咳が出る可能性が高いこともあり、コロナ禍ではこの検査は控えています。実施する時は、厳重な感染対策などを行った上で実施します。
嚥下造影検査(X線)
大病院にて可能な検査です。必要であればご紹介のうえ実施します。
接触嚥下障害の治療内容

具体的な訓練
食べ物を使う訓練(直接訓練)
- 食形態の変更(普通食→おかゆ→ペースト状→ミキサー状など)
- 水分にとろみをつける
- 食事時の姿勢の変更
- 食べ方の工夫(1回分の食べものを何回かに分けて、噛んで飲み込む)
- 食具の変更(食べやすい食器などの提案)
食べ物を使わない基礎的な訓練(間接訓練)
- 筋トレ→口唇・舌・頬を動かすトレーニング。口のまわりの筋力アップを図り、各器官の動きをスムーズに。
- のどのマッサージ→嚥下反射を促すマッサージ。
- 嚥下反射促進マッサージ→あごから下の筋肉をマッサージ。
- 発声訓練など
口腔内装置の使用
- 舌接触補助床(PAP)→舌の動きが悪くなっている患者さまに対して、舌の動きを促進。嚥下や発音を改善させる装置。
- 軟口蓋挙上装置(PLP)→軟口蓋(のどの奥の上側の柔らかい部分)の動きが悪くなっている患者さまに装着し、空気の鼻もれを防ぐために口と鼻を分離させ、嚥下や発音を改善させる装置。
訓練により、食べる楽しみを取り戻しましょう
こうした訓練や装置の使用についての治療期間は患者さまの状態によってそれぞれです。高齢の患者さまの場合は、機能を維持することが訓練の目的なので、終了という段階はなく、継続していきます。もちろん訓練の習慣が身につき、ご自身一人でできるようになれば、私たちの介入による治療は終了とみなすことができますが、症状が悪化した場合には、その状況に合わせた訓練を改めて指導します。
これまで担当した患者さまの中には、めざましい回復を遂げた方もいました。その方は、口から食べることができず、胃ろうをつくって生活していました。ところが、嚥下障害治療の訓練や歯科治療を行ったところ、時間はかかりましたが、最終的に普通食が食べられるまでに回復したのです。訓練次第では、どなたでも同じように食べる楽しみを再び得ることができます。
診療費
摂食嚥下障害の診療は、保険診療内で行います。詳しくは、お問い合わせください。